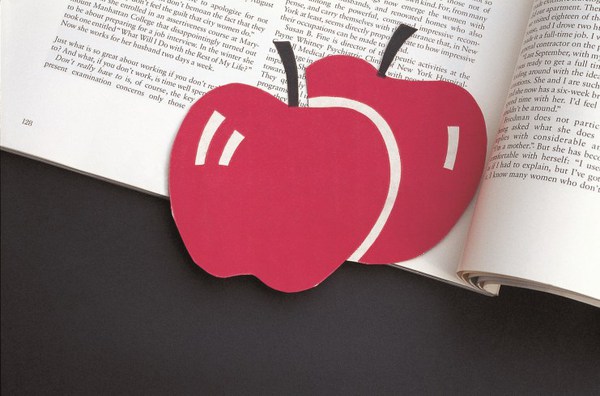「わかりました」
と彼は言った。
「父親から寿司店を引き継いで、いまはカウンターのなかで寿司を握っている、四十三歳の女性が、じつはハーレーのローライダーに乗っているのですね」
「洒落た顔立ちの美人で、少しだけ茶色にした髪が、いなせなのさ」
僕がそう補足した。補足するならいくらでも出来るが、いまはこのくらいでいいだろう。
「もうひとりの女性について、聞かせてください。二台のハーレーの物語ですよね。ふたりの女性たちが、どちらもハーレーのローライダーに乗っている、という物語」
「もうひとりは」
と、僕は言った。
「日本ではとにかく年齢をきめてしまう必要がある。彼女は十歳年下にしよう。だからいま彼女は三十三歳だよ」
「いいですね」
「なぜ?」
「距離の開き具合が。近いような、かなり遠くもあるような」
「そうだね。ふたりの女性たちのあいだにある十歳という年齢差。その上に、この物語のすべてが、支えられている」
わかったような、そうでもないような、曖昧な表情を彼は浮かべた。
「ふたりの女性それぞれを、書き手の僕は、描き分けなければいけない。くっきりと、鮮明に。ふたりのあいだにある十歳の年齢差に、書き手の僕も支えられる」
「十歳以外では駄目ですか」
「書く気にならないよ」
「そんなもんですか」
「そんなもん」
という僕の返事に彼は笑った。
「では、十歳若い彼女は、なにをしてる人ですか」
という彼の質問に、僕は次のように答えた。
「四十三歳の女性のほうの歴史や背景をこと細かに作っておく必要があると同時に、十歳若いほうの女性に関しても、歴史や背景はきちんと作っておかなくてはいけない。ひとり娘がいいかな。父親はチェロ奏者。クラシック音楽のね。ひとり娘の彼女は、音楽の才能を父親から引き継いでいる。寿司の店を引き継ぐのと、ほとんどおなじだよ」
「ははあ、そこに相似形があるんですか」
「彼女は音楽学校で作曲を勉強して卒業した。いろんな仕事をするわけだよ。スタジオ・ミュージシャン。ごく小規模なライヴ活動。幼い女のこたちにピアノを教える。日曜日に何人かの自宅を順番に訪ねて。かつてはジャズのビッグ・バンドでベースを担当していた。しかしドラムスに強く惹かれるものを制御しがたく、勉強と実地トレーニングを積み重ねて、きわめて優秀なドラムス奏者になった。仕事を追っていくと、生活も転々とするのさ。どんな転々も彼女はへっちゃらでこなしていく。このあたりの彼女の魅力は、きちんと書かなくてはいけない。日本にビッグ・バンドがなくなって、彼女はスウェーデンへいき、そこでビッグ・バンドに加わって一年間を過ごしたりする」
「一年ですか」
「一年過ごすと、日照時間の少なさが、彼女の身にしみる。イギリスのダンス・バンドに移るけれど、ここでも日照は少ない。彼女は沖縄に移る。海兵隊基地の軍楽隊のなかにジャズのビッグ・バンドがあり、軍隊とは関係していない一般市民の演奏者も参加出来る仕組みになっていて、もちろん日本の人でもOK。彼女はそこに参加する。だから沖縄に住むのさ。彼女は人気がある。細身のスタイルのいい女性で、いつもはやや冷たい顔なのだけど、笑顔になるとぱっと華やぐ。ドラミングはじつに美しい。海兵隊のビッグ・バンドを、一歩もひけをとることなく、どんな曲においても見事に屋台骨を支える」
「夢のようですね」
「すべては夢だよ」
「夢に徹する、ということですか」
「そうさ。こうして、一年、また一年と、人生の時間は経過していく。ふと気がつけば、三十三歳だよ。音大の頃の同級生の男性がロカビリー・バンドを作っていて、彼にぜひにと請われて、そのロカビリー・バンドのドラムスを引き受ける。しかし、食えないよ、これでは。このロカビリー・バンドは西のほうで人気がある。沖縄、鹿児島、熊本、宮崎、大分、そして博多。そこから瀬戸内を東へ、神戸まで。京都も根拠地のひとつだ。父親から引き継いで寿司を握っている女性の店は、瀬戸内にある。場所はまだきめていないけれど、瀬戸内のどこか。そしてロカビリー・バンドのツアーの途中、その寿司の店にバンドの連中と入ろうとして、満員で入れなかった、という体験があるけれど、三十三歳の彼女は、そんなことはとっくに忘れている」
「ニア・ミスですか」
伏線だよ、と僕は言いたかったが、黙っていた。ロカビリー・バンドのリード・ギターとヴォーカルの男性は、オートバイに乗っている。いっそのこと、彼のオートバイはインディアンにしよう。ヴィンテージのインディアンを維持して乗りながら、ロカビリー・バンドを運営する。楽ではない。楽ではなくて、しかも食えない。バンドと言っても、彼とドラムスの彼女、そしてあとふたりに、補欠のような位置にさらにふたりいるだけだが。
「インディアンですか」
「それしかないだろう」
「そうも言えます」
「彼女は彼がオートバイに乗ることは知っていたけれど、さして関心はなく、知らないと言ってもいい状態だった。ところが、ある日、なにげないふとした一瞬、彼の乗るインディアンにいきなりからめ取られた彼女は、自分もオートバイに乗ることを決意する。免許を取得するまで東京に落ち着き、彼女は免許を手に入れる」
「なるほど。彼女なりの歴史ですね」
「彼女はオートバイに乗る人になる」
四十三歳の彼女と、三十三歳の彼女とを、交互に書いていけばいい、という構成を僕は思いついた。ふたりの女性と二台のオートバイ。女性はまったく別人どおしだが、オートバイのほうは年式や色までおなじだ。このふたりの女性とオートバイを、交互に描いていく。おたがいにまだ知り合ってはいないのだが、交互に描かれる物語はまさに交互であり、その交互の積み重ねが一定の限度を越えると、ふたりはいつ、どこで、どのように出会うのか、ということがクライマックスとして、読者の意識のなかに芽生える。
「ふたりは出会うのですか」
という彼の質問に、
「せっかくだから出会わせたいじゃないか」
と、僕は答えた。
「物語ですからねえ」
「出会うまでの物語」
「ははあ」
「二人ともお互いの存在などまるで知らないままに、ふたりの距離が少しずつ詰まっていく」
「サスペンスですね」
「うまくいけば。書き手としての僕に、それだけの腕力があるなら」
「試してくださいよ」
「いつ、どこで、どんなふうに出会うのか。その一瞬に向けての、二台のローライダーによる、ふたりの美しい女性たちによる、サスペンス物語」
「読ませてください」
「文字どおりの、ごく普通の出会いではなく。初めまして、こんにちわ、などではなく。出会ってはいるけれど、次の瞬間には、ふたりは別れている。どこの誰なのか、おたがいに知らないままに」
「わかりました」
と、彼の声が大きくなった。
「すれ違ってるわけですね」
「二台のローライダーで、ふたりの女性たちが。道路とはストレートとカーヴ、そしてアップとダウン」
「カーヴだ」
と、彼は言った。彼は正しい。カーヴのなかで、ふたりはすれ違う。日本じゅう、いたるところ、どこにでもあるような、平凡なカーヴ。しかしその平凡さにおいて、唯一無二のようなカーヴ。二台のローライダーが、それぞれ反対方向から、そのカーヴに入って来る。カーヴの頂点で二台はすれ違う。二台はそれぞれカーヴのなかに向けて、つまり相手に向けて、傾いている。すれ違いはほんの一瞬だ。年かさのほうが、グリップにある右手の人さし指から小指までの四本を、すれ違う瞬間、軽く立てる。すれ違いの挨拶だ。年下のほうはそれをはっきりと視認する。
「そこで終わるといいよ。カーヴへと入っていく二台を克明に描写して。すれ違う瞬間に関しても的確な言葉をつくして」
いま僕が考えている、二台のオートバイとふたりの女性たちによる物語とは、ごくおおまかに述べて、以上のようなものだ。カーヴのまんなかですれ違う一瞬、という普遍性がクライマックスとして設定されていて、それまでのすべてがそこへと帰結していく物語。オートバイの物語はこれしかない、といまは思っている。